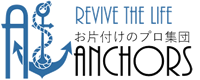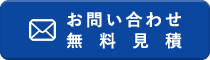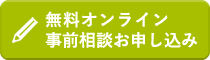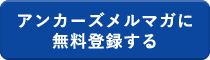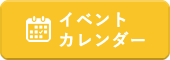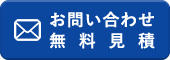711/1000 アンゾフのマトリクスが教えてくれた「決断の質」
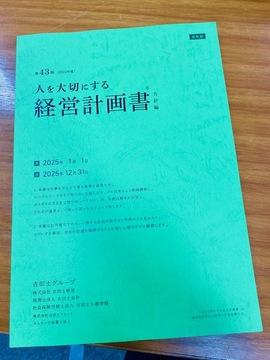
経営計画書作成合宿セミナー二日目。
講師は株式会社古田土経営(古田土会計グループ)。
経営計画書の作り方だけでなく、その“使い方”を徹底的に指導してくれる実践派。
今回の大きなテーマは「数字 × 戦略の質 × 行動の量」。
本日は戦略の質と行動の量にフォーカスした一日でした。
午前中は、弱者の戦い方として知られるランチェスター戦略をベースに、
「誰に」「何を」「どうやって」届けるのかを再定義。
改めてペルソナを設定し、なぜお客様が自社の商品を選ぶのかを掘り下げていきました。
やってみると、これまで“ニーズ”だと思っていたものが、実は自社の“シーズ(種)”であったり、
“お客様目線”のつもりが、実は自分たち都合の押し売りだったり。
気づきの多い時間となりました。
そして午後、一番心に残ったのが、アンゾフの成長マトリクスを使った「新規事業の決断」に関する講義でした。
既存市場 × 既存商品から始まり、新市場・新商品へと進む4つの方向性。
この図を、単なる“成長理論”ではなく、リスクと覚悟を見える化するツールとして解説されたのが非常に印象的でした。
講師の言葉が心に残ります。
「どこにリスクがあるかを見える化できれば、迷いではなく戦略になる。」
新市場 × 新商品、つまり“多角化”へ踏み出すとき、
人はつい夢や勢いで動きがちです。
しかし、アンゾフのマトリクスを冷静に当てはめると、
感情ではなく構造で判断できる。まさに意思決定の羅針盤です。
私はこれまで、どちらかと言えば直感で動くタイプでした。
けれど今日の学びで、直感に“理論の補助線”を引くことの大切さを実感しました。
「新しい挑戦をする」というのは、単に勇気を出すことではなく、
自社の立ち位置を見極め、進むべき方向を言語化すること。
その決断こそが、戦略の質を高める行為なのだと感じました。
数字 × 戦略の質 × 行動の量。
経営の結果をつくるこの方程式の中で、今日は「決断の質」を磨いた一日。
勢いではなく、確信をもって一歩を踏み出すための“思考の軸”を得られた、濃い二日目となりました。-
 796/1000 寡黙な職人
きょうで、一大プロジェクトの工事が終わった。詳細は、これから小出しにしていこうと思う。この一年でいちばん寒い時
796/1000 寡黙な職人
きょうで、一大プロジェクトの工事が終わった。詳細は、これから小出しにしていこうと思う。この一年でいちばん寒い時
-
 798/1000 求められる自分と本当の自分
久々の二連休初日。それなのに、朝からなんだかそわそわしている。仕事をしていないと落ち着かない。もう体が、そうい
798/1000 求められる自分と本当の自分
久々の二連休初日。それなのに、朝からなんだかそわそわしている。仕事をしていないと落ち着かない。もう体が、そうい
-
 800/1000 三十年越しの『BIG』
Netflixで、トム・ハンクス主演の『BIG』を、高校一年生ぶりに観た。気づけば、三十年ぶりくらいになる。当
800/1000 三十年越しの『BIG』
Netflixで、トム・ハンクス主演の『BIG』を、高校一年生ぶりに観た。気づけば、三十年ぶりくらいになる。当
-
 802/1000 たまには一人がいいね
東京出張1日目が終わった。予定が終了して、一目散に向かったのは、ホテル。そしてそのあとはもちろん、どこにも行か
802/1000 たまには一人がいいね
東京出張1日目が終わった。予定が終了して、一目散に向かったのは、ホテル。そしてそのあとはもちろん、どこにも行か
-
 804/1000 予定のないドレスの話。未来の話ができるのが嬉しい
二泊三日の東京出張が終わり、雪の庄内に帰る。飛行場に止めた車の雪が心配だ。今回は中期経営計画を作成する合宿セミ
804/1000 予定のないドレスの話。未来の話ができるのが嬉しい
二泊三日の東京出張が終わり、雪の庄内に帰る。飛行場に止めた車の雪が心配だ。今回は中期経営計画を作成する合宿セミ