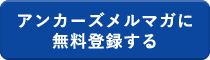- ホーム
- 毎日ブログ
毎日ブログ
685/1000 携帯がつながらない時代の間接フリーキック
2025/10/01
最近ちょっと困っていることがあります。
それは「携帯電話から高齢者宅に電話をしても繋がらない」こと。
先日、私の携帯電話に「こちら山形県警捜査二課ですが…」と名乗る男性から電話がかかってきました。もちろん、次の言葉を聞く前に即切り。ドキッとしたのは事実ですが、詐欺電話に付き合うほど暇ではありません。
ただ一瞬、「捜査二課って『地面師たち』で辰さんがいた課だっけ?いや辰さんは警視庁の捜査二課か?」と、訳のわからない思考に迷い込んでしまいました。
それにしても、最近こうした正体不明の電話がやたら多いと聞きます。
だからでしょうか、本当に仕事で電話をしても出てもらえない。せめて留守電のメッセージから折り返していただければありがたいのですが、たいてい音信不通のまま。
結局どうするかというと、事務所の固定電話から掛け直すことになります。
携帯がダメなら固定から。これではまるで「間接フリーキック」。
相手から急ぎで!と指定されているのに、どうしてもワンクッション置かされる。
世の中の不安に備えるのは大事ですが、仕事の電話まで警戒されるのはちょっと切ない。
安心して電話ができる世の中、これからの課題かもしれませんね。683/1000 10月こそベストシーズン、お片付けのすすめ
2025/09/29
自販機に温かい飲み物が並びはじめ、秋の深まりを一層感じるようになりました。
この時期、ホテルでは夏に大活躍したグッズを片付け、冬に向けた準備が始まります。そのため、ホテルからの粗大ごみ収集のご依頼も一気に増えてくるのです。
一般的に「お片付けは年末」というイメージが根強く、実際に私たちへの講演依頼も12月に集中します。ですが、12月に入ってからではすでに遅いのが現実。寒さに震えながら片付けるのは大変ですし、慌ただしい年末の時間の中で腰を据えて取り組むのは至難の業です。
その点、10月は暑くもなく寒くもない、まさにお片付けのベストシーズン。落ち着いて家と向き合い、暮らしを整えるのにぴったりのタイミングです。
年末に「もっと早くやっておけばよかった」と後悔しないためにも、今年は少し前倒しで動き出してみませんか。
片付いた空間は、心の余裕にもつながります。きれいに整った部屋で迎える冬、そして新しい年は、きっとこれまで以上に穏やかで気持ちよいものになるはずです。681/1000 偉い人ほど約束、破りがち
2025/09/27
無印良品酒田でのイベント初日が終わりました。
私は「わけるとわかるわけるくんインストラクター」として参加者のみなさんと一緒に、片づけの癖や心の癖を探るワークを行いました。
無印良品では「からだとくらしの広場」と題して、地域のみなさんとつながりながら暮らしに役立つ体験や学びの場をつくっています。食や住まい、健康や学びといった日々の暮らしを豊かにするテーマを、地域の人や団体と一緒に育てていく取り組みです。今回のイベントもその一環として開催され、庄内お片づけ部として参加させていただきました。
「わけるくん」とは、モノの整理を通して自分の価値観や思考のクセに気づけるカードゲームのようなワークです。様々な種類のカードを自分が定めたルールで分けていくうちに、人それぞれの判断軸やこだわりが浮き彫りになるのが特徴。遊び感覚で取り組めるのに、整理の本質が見えてくる優れものです。
そんな「わけるくん」での体験の中で、ある方が語った言葉が胸に刺さりました。
「ルールは大切。だから守ろうとするのは尊いこと。でも決まって守らないのは、上に立つ人、偉い人なんですよね」
ふと、政治や社会の姿が重なります。法律や制度といった「ルール」を守るのは、多くの市民や現場の人たち。ところが、発言力や権力を持つ側がそのルールを逸脱し、結果として下の立場の人が後始末を担わされる。しかもその努力は、ほとんど評価されることがありません。
社会に限らず、組織の中でも同じことが起こりがちです。ルールをつくる側であるほど、その重みを忘れてはいけない。そう教えられた気がしました。
今日のワークで得た気づきは、自分自身への戒めでもあります。立場が上になるほど、ルールを軽視しがちなのかもしれない。そうならないように、まず自分が律すること。それが、まわりへの何よりのメッセージになるのだと思います。
そして明日28日(日曜日)14時〜17時、会場にてまたみなさんとお会いできるのを楽しみにしています。677/1000 お彼岸に義父とともに
2025/09/23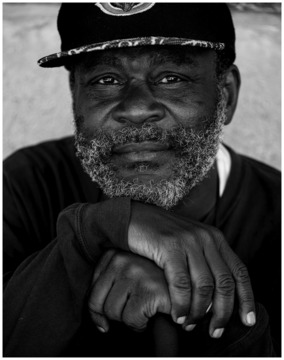
お彼岸ということで、妻の実家のお墓参りに出かけました。
義父はいつになく陽気で、孫たちと並んで写真を撮りたがったり、いつもは家で待っているのですが、一緒に墓参りに行った私を開山堂へ案内してくれたりしました。
その姿に「今日は特別だな」と感じていたのですが、ふとした拍子に義父の口から出てきた言葉が、少し胸に残ります。
「そろそろ終活しなきゃな」
「今の写真は遺影に使って欲しい」
「この家を片付けると、どのくらいかかるんだ?」
笑顔の裏にちらつく現実。冗談半分に聞こえながらも、その一言一言が心配になってしまう。
けれど同時に、こうして自分のことを笑いながら語れるのは、元気でいる証なのかもしれません。
お墓参りを終え、帰りに買ったアイスクリームをみんなで食べながら撮った写真の義父は、少し子どものように無邪気な笑顔でした。
その写真を家族のLINEグループにアップすると、東京にいる娘たちからすぐに返信がありました。
「じい、かわいいね」
「背抜かれたね」
「久しぶりに行きたいな〜実家」
そんな言葉に画面越しに笑い合う家族。離れていても、ひとつの笑顔でつながる瞬間がありました。
その笑顔を見ていると、「まだまだこれから」と思いたくなるのです。675/1000 知らなければ同じ、知ればまるで別物
2025/09/21
似ているけど、見る人が見るとまったく違うものってあります。
私が今、初段を目指して練習している習字なんかもそうです。興味のない人に言わせれば「どっちも上手いじゃん」で終わってしまう。けれど、筆の入りや払い、余白の取り方を知れば知るほど、見え方が変わってくる。自分の字の稚拙さに気づかされるのと同時に、奥深さがどんどん顔を出してくるのです。
同じことを、この頃はじめたコーヒーのハンドドリップでも体験しました。最初に淹れた一杯が偶然にも好評で、プロから「豆の旨みをストレートに表現している」と褒められ、すっかり気を良くしてしまった私。ところが、二杯目からはどうにも再現できない。何度淹れてもあの味に届かず、ただただスランプの中でもがいております。
温度計を買い、ミルの荒さを変えてみたり、お湯を注ぐ(置く)速度を調整したり。小さな変化を繰り返しては試し、繰り返しては悩む。そのたびに妻は「美味しいよ」と言ってくれるのですが、自分の中ではどうにも納得がいかない。凝り性と言われればそれまでですが、その「納得のいかなさ」こそが、実は面白くて仕方がないのです。
知らなければ「どれも同じ」で済んでしまうこと。けれど一歩踏み込んだときに見えてくる違いが、日常を深くしていく。
習字もコーヒーも、結局はその繰り返しにハマっているのだと思います。-
 796/1000 寡黙な職人
きょうで、一大プロジェクトの工事が終わった。詳細は、これから小出しにしていこうと思う。この一年でいちばん寒い時
796/1000 寡黙な職人
きょうで、一大プロジェクトの工事が終わった。詳細は、これから小出しにしていこうと思う。この一年でいちばん寒い時
-
 798/1000 求められる自分と本当の自分
久々の二連休初日。それなのに、朝からなんだかそわそわしている。仕事をしていないと落ち着かない。もう体が、そうい
798/1000 求められる自分と本当の自分
久々の二連休初日。それなのに、朝からなんだかそわそわしている。仕事をしていないと落ち着かない。もう体が、そうい
-
 800/1000 三十年越しの『BIG』
Netflixで、トム・ハンクス主演の『BIG』を、高校一年生ぶりに観た。気づけば、三十年ぶりくらいになる。当
800/1000 三十年越しの『BIG』
Netflixで、トム・ハンクス主演の『BIG』を、高校一年生ぶりに観た。気づけば、三十年ぶりくらいになる。当
-
 802/1000 たまには一人がいいね
東京出張1日目が終わった。予定が終了して、一目散に向かったのは、ホテル。そしてそのあとはもちろん、どこにも行か
802/1000 たまには一人がいいね
東京出張1日目が終わった。予定が終了して、一目散に向かったのは、ホテル。そしてそのあとはもちろん、どこにも行か
-
 804/1000 予定のないドレスの話。未来の話ができるのが嬉しい
二泊三日の東京出張が終わり、雪の庄内に帰る。飛行場に止めた車の雪が心配だ。今回は中期経営計画を作成する合宿セミ
804/1000 予定のないドレスの話。未来の話ができるのが嬉しい
二泊三日の東京出張が終わり、雪の庄内に帰る。飛行場に止めた車の雪が心配だ。今回は中期経営計画を作成する合宿セミ